第8回 禁断のブラック、ぶった切り回答 Q&A
投稿日:
執筆者:empowerment
School Social Workers・Well-Being・Project
投稿日:
執筆者:empowerment
関連記事

『学校現場における外国籍生徒の支援の現状と課題:外国ルーツ者支援のNPOの紹介を含めて』
サタデーナイト研修 7月10日(土)19:00~20:30 報告 伊勢崎市・安中市SSWr 原口一美 様 ・伊勢崎市の状況 ・外国人の文化の違い(主観) ・NPO紹介 ・5つの事例紹介 ・課題と情報共 …
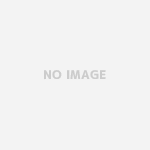
山口県や島根県でスーパーバイザーとして活動されてきた 岩金俊充様 により新しく新人スクールソーシャルワーカーのためのエッセンスをお届けします。 内容はいつ見ても色あせず温かな笑いさえ生みながら専門的な …

岩金俊充 #なんだかんだで5回目です。 #新人のsswrのための連載 猛暑かと思えば大雨、地球はいったいどうなっているのでしょうか? #みなさまの地域は大丈夫でしょうか 犬の散歩をしていると、犬が寝っ …
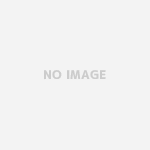
自己受容尺度の活用に関するお問い合わせをいくつもいただいておりましたので尺度の掲載を致します。活用する場合はぜひ研究結果の報告をいただけますと幸いです。本サイトでお知らせしたいと思います。 加えて、様 …